【2025年最新版】特定技能「自動車運送業」とは?試験内容・申請方法・受け入れのポイントを解説
- sou takahashi
- 2025年4月25日
- 読了時間: 12分
更新日:2025年5月27日

日本の自動車運送業界では深刻な人手不足が続く中、「特定技能1号」による海外人材ドライバーの受け入れが本格化しています。
本記事では、制度の概要から試験対策、受け入れ企業の注意点までをわかりやすく解説。これから働きたい人、雇いたい企業の両方に役立つ情報が満載です。
1.特定技能自動車運送業の制度とは

在留資格「特定技能1号」の概要
在留資格「特定技能1号」は、日本の深刻な人手不足を補うために創設された制度です。特に中小企業が多く、採用が困難な業界において、即戦力となる海外人材の就労を可能にする仕組みです。
特定技能 自動車運送業分野社員採用について
一定の技能や知識を持つことが条件であり、業種ごとに設けられた試験に合格する必要があります。
この資格では、介護や建設、宿泊業など16分野での受け入れが認められており、自動車運送業もその一つです。滞在期間は最長で5年、家族の帯同は基本的に認められていません。また、日本語能力試験(N4相当)と業種別の技能評価試験の両方に合格することが求められます。
これにより、即戦力の海外人材が日本国内で働く道が開かれ、企業にとっても安定的な労働力確保が可能となります。ただし、資格取得後も雇用側のサポート体制や生活支援が義務付けられている点には注意が必要です。
自動車運送業が対象になった理由
自動車運送業が特定技能の対象分野に追加された背景には、業界の慢性的な人手不足があります。特に高齢化と若年層の離職が進む中、運転業務を担う人材の確保が大きな課題となっていました。
この分野は、トラック・バス・タクシーといった公共性の高いインフラを支える産業であり、人員の不足が社会全体の物流や移動に深刻な影響を及ぼすため、国も早急な対策を必要としていました。国内の人材確保に努めたものの、十分な人材を集めることができなかったため、海外人材の導入に踏み切った形です。
加えて、業界団体や企業側の強い要望もあり、制度整備が進められました。2024年からは特定技能1号の制度に基づき、海外人材ドライバーの受け入れが本格化しています。今後も業界全体での研修体制や多言語対応の強化が求められています。
海外人材の受け入れに関する国の方針
日本政府は、単なる労働力不足の補填ではなく、適切な条件下での海外人材の受け入れを重視しています。そのため、「特定技能」の制度では、受け入れ企業に対して生活支援や教育体制の整備が義務付けられています。
具体的には、労働環境の整備、日本語学習支援、相談体制の構築などが挙げられます。また、海外人労働者が安心して働き続けられるよう、監督機関による定期的なチェックも行われます。これにより、技能実習制度で問題となっていた劣悪な労働環境の再発を防ぐ狙いがあります。
加えて、出入国在留管理庁や厚生労働省はガイドラインを策定し、制度の透明性を高めています。これは、受け入れ企業にとっても基準が明確になるメリットがあり、トラブルの未然防止にもつながります。全体として、公正で持続可能な受け入れ体制の構築が進められている状況です。
2.特定技能自動車運送業で働ける仕事内容

トラック・バス・タクシー運転の具体的な業務
自動車運送業における特定技能の対象となる業務は、トラック、バス、タクシーの各種車両を用いた運転業務です。
トラック運転手は主に物流を支え、荷物の積み下ろしや配送先との調整も行います。
バス運転手は通勤や観光などで利用される路線・貸切バスを運行し、時間や安全運転が重視されます。
タクシー運転手は乗客を安全に目的地へ送ることが業務の中心で、接客マナーや土地勘も求められます。
いずれも車両管理や簡単な整備作業、日報作成などの付随業務が含まれることが多く、単なる「運転」だけでない幅広い対応が求められるのが特徴です。特定技能の試験に合格すれば、これらの業務に即戦力として従事できるようになります。
特定技能 自動車運送業分野社員採用について
必要な技能や資格のレベル感
特定技能で自動車運送業に就くには、日本語能力と運転に関する技能の両方が必要です。日本語については、日常会話や業務指示を理解できる「日本語能力試験N4レベル」が目安となります。
運転技能については、特定技能1号評価試験(自動車運送業分野)に合格することが求められており、この試験では運転業務に必要な知識や安全に関する理解、法令順守の意識などが問われます。なお、実際に就労するためには日本国内で有効な運転免許を取得しなければならないため、免許の切替や新規取得も必要になります。
これらの要件は「初心者向け」ではなく、一定の経験や理解力が前提とされているため、事前の準備や学習が不可欠です。
労働環境と雇用条件のポイント
自動車運送業における海外人材の労働環境は、法令に則って整備される必要があります。基本的には日本人労働者と同等の待遇が保証され、賃金・労働時間・休暇などの条件も公平に扱われます。
ただし、職場によっては長時間労働や休日出勤があるため、就職前に契約内容をしっかり確認することが重要です。雇用条件においては、社会保険の加入や健康診断の実施、日本語学習の支援といった点も含まれ、受け入れ企業にはこれらの整備が義務付けられています。
また、海外人材向けに生活支援体制を整えている企業も多く、住居の確保や地域情報の提供、相談窓口の設置なども進められています。安心して働くには、労働環境の実態やサポート内容を事前に調べることが欠かせません。
3.特定技能自動車運送業の試験内容と申込方法

評価試験の内容と難易度
特定技能「自動車運送業」分野の評価試験は、海外人材労働者が日本でトラック、タクシー、バスのドライバーとして就労するために必要な知識と技能を確認するためのものです。
試験は学科試験と実技試験の2部構成で行われます。
学科試験 | 運行業務や安全衛生に関する知識を問う○×形式の問題が30問出題されます。 |
実技試験 | 三肢択一形式の問題が20問出題され、実務的な技能が評価されます。 |
合格基準は、学科・実技ともに正答率60%以上とされています。
試験の難易度は、過去の合格率から見ると比較的高い合格率を示しています。
例えば、2024年12月に実施された試験では、トラック区分の合格率が約72.6%、バス区分およびタクシー区分では100%の合格率が報告されています。
このように、適切な準備を行えば、合格の可能性は高いと考えられます。
試験の申し込み手順と必要書類
特定技能「自動車運送業」分野の評価試験の申し込みは、以下の手順で行われます。
受験資格の確認 | 試験実施日において、満17歳以上であり、有効な日本または外国で取得した自動車運転免許を保有していることが必要です。 |
試験方式の選択 | 試験は、個人申請によるCBT(コンピューター・ベースド・テスト)方式と、法人申請による出張試験方式の2種類があります。 |
申し込み | 日本海事協会の特定技能試験ポータルサイト |
必要書類の提出 | 申し込み時には、運転免許証(両面)や在留カード(両面)もしくはパスポートのコピーが必要です。 |
受験料の支払い | 受験料は5,000円(税抜)で、支払いはクレジットカードのみとなっています。 |
これらの手順を踏んで、試験の申し込みを完了させることができます。
試験を実施する日本海事協会の役割
一般財団法人日本海事協会(ClassNK)は、特定技能「自動車運送業」分野の評価試験の実施主体として指定されています。

同協会は、国土交通省などの関係省庁からの指定を受け、試験の企画・運営を行っています。
具体的には、試験の内容の策定、試験会場の設営、試験の実施、合否の判定、合格証明書の発行など、試験に関する全般的な業務を担っています。
また、受験者の利便性を高めるために、CBT方式の導入や、海外での試験実施など、試験の柔軟な運営にも取り組んでいます。
このように、日本海事協会は、特定技能制度の円滑な運用と、海外人材労働者の適正な受け入れに重要な役割を果たしています。
4.特定技能自動車運送業の試験対策方法
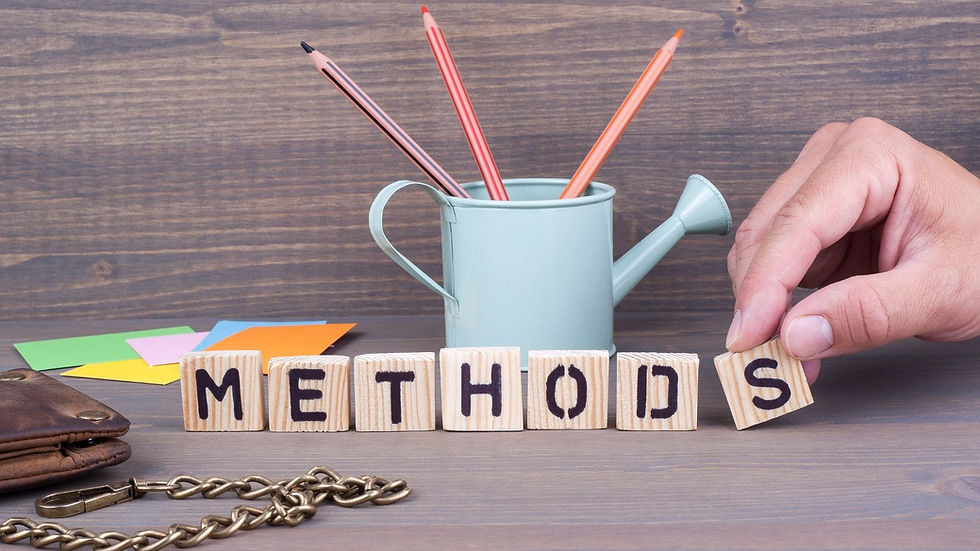
効率的な学習の進め方
特定技能「自動車運送業」分野の評価試験に向けた学習は、段階的かつ実践的に進めることが重要です。
まず、出題範囲の全体像を把握し、学科と実技の内容を分けて理解することから始めましょう。学科試験では運行管理や交通法規、安全対策などが中心となるため、公式のシラバスや出題例を活用して知識の整理を行うと効果的です。
一方、実技試験では、現場で想定される運転状況や接客マナーなども問われるため、動画教材や過去の模擬問題を使って実践感覚を養うことが求められます。
さらに、スケジュール管理を徹底し、毎日決まった時間に学習する習慣をつけることで、記憶の定着が良くなります。焦らずにコツコツ取り組む姿勢が、効率的な学習のカギとなります。
試験対策に使える教材・参考資料
特定技能「自動車運送業」分野の評価試験に対応する教材は、多様な形式で提供されています。まず、日本海事協会が公式に公開している「出題範囲」や「サンプル問題」は、必ず目を通すべき基本資料です。
これらは、試験で出題される問題の傾向や難易度を知る上で欠かせません。また、民間の研修機関や海外人材支援団体が提供する対策講座や模擬試験もあります。特に多言語対応の教材は、日本語が不安な受験者にとって大きな支えになります。
さらに、YouTubeなどで公開されている運転技能や交通ルールの解説動画も、視覚的に理解を深める助けになります。こうした資料を組み合わせ、自分に合った学習スタイルを確立することで、合格に近づくことができます。
合格後の流れと必要な手続き
評価試験に合格した後は、就労に向けた在留資格の申請手続きが必要となります。
まず、合格証明書を取得し、雇用先となる企業と正式な契約を結びます。その後、企業を通じて「特定技能1号」の在留資格認定証明書を出入国在留管理庁に申請します。この際、雇用契約書や住居情報、支援計画書などの提出が求められます。
また、国内に在留している場合は在留資格の変更申請、海外にいる場合は在留資格認定証明書の交付を受けた上で、日本の在外公館でビザの発給を受ける流れです。在留資格取得後は、定期的に技能実習機関や自治体の支援を受けながら、安定した就労と生活を始めることになります。
手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、受け入れ機関や支援団体がサポートする体制が整っているため、安心して準備を進めることができます。
5.特定技能自動車運送業に関する最新情報

CBT試験導入とPearson VUEの仕組み
CBT(Computer Based Testing)試験の導入により、特定技能「自動車運送業」分野の評価試験は、より柔軟かつ効率的に実施されるようになりました。
CBT方式では、受験者がコンピューター上で問題を解く形式となっており、試験日や会場を自分の都合に合わせて選べるのが大きなメリットです。この仕組みを支えるのが、世界的な試験運営会社であるPearson VUEです。
同社のネットワークを通じて、日本国内はもちろん海外でも受験が可能となっており、海外人材の利便性が大きく向上しています。試験会場では本人確認や監視体制が厳格に管理されており、公平性とセキュリティが担保されています。
受験環境が整っていることから、スムーズに試験を受けられる点でも高く評価されています。
制度改正のポイントと運用要領の変更点
特定技能制度における最新の改正では、海外人材の受け入れ体制を強化し、実務に直結した制度運用が重視されるようになりました。2024年以降の運用要領では、雇用契約や支援体制の明確化が求められるなど、企業と海外人材の双方にとって安心できる仕組みづくりが進められています。
とくに「特定技能1号」に関しては、労働条件の明記、定期的な面談、言語サポートなどを含む「支援計画書」の提出が義務化され、受け入れ企業の責任がより明確になっています。
また、自動車運送業分野に関するガイドラインも新たに整備され、交通安全や労働環境への配慮が制度上でも強く打ち出されています。こうした改正は、制度の信頼性向上と円滑な運用を目的としています。
6.まとめ

特定技能「自動車運送業」制度は、日本の物流と公共交通を支える重要な施策です。海外人材にとっては日本でのキャリアを築くチャンスであり、企業にとっては慢性的な人手不足を補う有効な手段となります。
特定技能 自動車運送業分野社員採用について
ただし、制度の活用には正確な情報と準備が不可欠です。試験の内容や申請手続き、雇用後の支援体制など、あらゆる面での理解と対応が求められます。
今後も制度の見直しや運用変更が続く可能性があるため、常に最新情報をキャッチし、柔軟に対応することが重要です。正しい知識と誠実な対応が、海外人材と企業双方にとって持続可能な未来を築く鍵となるでしょう。
特定技能に強い登録支援機関 GLORY OF BRIDGE
GLORY OF BRIDGEは、特定技能の分野で 高品質な海外人材の紹介・支援を行う登録支援機関です。これまでに580名以上の特定技能社員の採用を成功させており、ビザ申請の認定率は100% という確かな実績を誇ります。
特に インドネシアやベトナムに自社の送り出し機関を持つため、現地での人材確保から日本での定着支援まで、一貫したサポートを提供できます。また、24時間対応の多言語サポートを実施し、入社後のトラブルや不安を解消。こうした充実したフォロー体制により、他社と比べ4分の1の低離職率を実現しています。
「海外人材の採用が初めてで不安」「せっかく雇った海外人材スタッフが定着しない」「特定技能人材を活用したいが、どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひGLORY OF BRIDGEにご相談ください。経験豊富な専門チームが、貴社の人材確保を全力でサポートいたします。



コメント